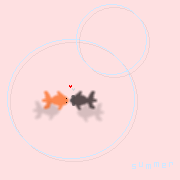金魚鉢の中には黒い出目金と真っ赤な金魚がヒラヒラと泳いでいる。昨年の夏から一年間無事生きてきた二匹はとても仲良しだ。
「シンちゃんの嘘つき」
自分の部屋にある。まるい縁取りがヒラヒラした金魚鉢を眺めながら、目にうっすらと涙を溜めて千恵美はつぶやいた。
去年の夏に約束したのだ、来年もちゃんとここに遊びに来ると、それなのに。
「シンちゃん今年は塾のゼミを申し込んだみたいで、夏祭りに来られないらしいわよ」
つい先程夕食の席で母親から聞かされたその言葉は、千恵美に大きなショックを与えた。
だから、その後続く母の話も右から左へと抜けてしまう。
ご飯茶碗を持ったまま呆然としている千恵美のおかずの皿から、育ち盛りの弟の健太が、メインのハンバーグを失敬していても、全く気づかない。そんな状態に何を言っても無駄だと悟った両親と弟はそのまま食事を続けた。
父親の弟の息子で、毎年夏になると都会から遊びに来る自分より一つ年上の従兄弟の新太郎と過ごす夏休みの一週間は、千恵美にとって一年で一番楽しみにしていると言っても過言ではないというのに、こんな訳であっさりとその楽しみは消えてしまったのだ。
また一緒に夏祭りに行って、去年の子供っぽい朝顔模様の浴衣に兵児帯なんかじゃなくて藍色の生地で裾に赤い金魚の柄の浴衣姿を見せてやろうなんて考えていたのに。
それに去年「死んでしまうと悲しいから要らない」と引き止めているのを「いいから、いいから」と勝手に金魚すくいをしてしまい。
「これ、来年俺が来たときにはでっかくなってるように大事に育てろよ」
なんて言って、その戦利品の金魚を自分に押し付けた新太郎が今年は来ないなんて。
約束を守ってちゃんと世話をし続けたのは、金魚が死んでしまうのが悲しいのもあるけれど、新太郎との約束(かなり一方的ではあるものの)を守ったからなのに。
仲良く泳ぐ金魚を見ているとどんどん悲しくなってくる。
千恵美は金魚にまで嫉妬してしまいそうな自分が滑稽だと、ますます落ち込んで布団の中に頭までスッポリともぐりこんだが、やがてその暑苦しさと悲しさに布団をベットの下に投げ捨ててしまった。
夏祭りの日。弟の健太は、母親の用意した浴衣を「そんな恥ずかしいもの着れねぇーよ」と言ってさっさと家を飛び出していった。
着付けを終えた千恵美は、馴れない帯が苦しいのもあって、浮かない顔で待ち合わせまでの時間を潰している。
「もう、そんな不細工な顔しないの。せっかくの浴衣が台無しじゃない」
母親の一言に、自分の顔が自然とぶすくれていたことに気づいて、慌てて洗面台の前の鏡を覗き込む。
今年の夏祭りは新太郎と一緒に行けなくなったと、クラスメイトで親友陽子ちゃんに伝えると「だったら今年は私と一緒にお祭り行こう」彼女は下手に慰めることもしないでそう言ってくれた。彼女が幼馴染の男の子と一緒に夏祭りに参加するのを毎年の恒例にしていることを千恵美は知っていた。それと彼女の仄かな恋心も。
「だって悪いよ、せっかくのデートなのに」
「でも、千恵美とはこの機会逃したらお祭り一緒に行けないかもしれないじゃない、こんなチャンス見逃すの勿体無いって」
なんでもないことのように答えて「楽しみだな」と心から言ってくれる親友がありがたくって、千恵美はその言葉に何度も頷いた。
だから、こんな顔を陽子ちゃんに見せるわけに行かないし、初めての『親友と一緒のお祭り』を楽しみにしてるのも本当だから、浴衣が濡れないように注意しながら冷たい水でパシャパシャ顔を洗って気を引き締めてから、初めて使うピンクのリップを唇にキュット引いた。
「うん、今度はちゃんと可愛いじゃない、いってらっしゃい」
母親がそう言って送り出してくれるのに、千恵美は元気良く「いってきます」と返事をして出かけていった。
初めての女同士の夏祭りは、思った以上に楽しかった。
「あっ、千恵美そのリップ新しいのだね、可愛いピンクで良く似合ってるよ」
待ち合わせの場所に到着した千恵美に気づいて声をかけた陽子は、いつものお下げ髪を解いて結い上げた纏め髪でうなじの辺りが色っぽい、声をかけられなければきっと気づかなかっただろう。
「陽子ちゃんは、凄く大人っぽくてなんか、違う人みたいでドキドキするよ」
「やだ何言ってるのよ」
キャラキャラと笑う仕草は普段の彼女と同じで、ちょっとした人見知りも一瞬のことだった。
それから二人は沢山の屋台を見て周り、途中で健太達を見つけてその暴れっぷりに声は掛けずに陽子と二人でコッソリと笑ってしまった。
祭りの〆となるお楽しみの花火もこの村唯一の娯楽とばかりにそれはもう見事であった。
今年始まった、打ち上げ花火とともにプロポーズをしようという企画に乗っかったカップルも居て、プロポーズの言葉と共に花火を打ち上げて貰っていた。
公衆の面前のプロポーズに「されたほうは、ちょっと恥ずかしいよね」と、二人で言ってはいたものの、実は羨ましくもあたりするのが乙女心でもあったりする。
「来年は彼氏と一緒に見たいよね」どちらともなくそんなことを自然と口に出していた。
しかし、ついてないことに最後の最後に、馴れない下駄の鼻緒のおかげで足の皮がめくれてしまった千恵美は、万が一に備えて持って行ったバンソウコウで応急処置をしてなんとか、家に戻ることが出来た。
「来年は捨てちゃうからね」
忌々しい下駄を脱ぐと、それをギット睨み付けた。
「ただいま」と言いながら傷む足を引きずって居間に入ったら、そこにはあまりにびっくりして、痛みなど吹き飛んでしまうことがあった。
お土産に買ったりんご飴が手から離れてボトリと畳の上に落ちる。
何故なら、ここに居るはずも無い新太郎が縁側でスイカを食べて寛いでいたからだ。
「おう、お帰り早かったな。チィの分のスイカは冷蔵庫ん中だってさ」
「なんで、なんで新ちゃんがここに居るの」
呆然とした様子で、つぶやく千恵美の様子に首をひねりながら新太郎は台所に向かって声を掛ける。
「ねぇ、美佐江おばちゃん、チィに俺来ること伝えてなかったの?」
「私はちゃんと言いましたよ。お祭りには間に合わないけど、ゼミの後には来るって。でもこの子ったらあの時ボーットしちゃってたから、聞こえてなかったのかもしれないわね」
台所から現れた母は、お皿に乗ったスイカをちゃぶ台の上に置いてくれた。心の準備が出来ていないのに、この突然の嬉しい出来事で、固まって突っ立ったままだった千恵美はりんご飴を落としたことに気づいて慌てて拾って。
「着替えてくる」と、言って自分の部屋に戻ろうとした。
「えーっ、何で。せっかく可愛いんだからチィもう少し着てろよ」
新太郎のこの一言に、手にしたりんご飴を又落とすところだった。
(今、新ちゃん私のこと可愛いって言ってくれた?)
「新ちゃんは暫く会わないうちに口が上手くなったわね」
そんな母の軽口に、なんだ冗談だったのかと、半分ホッとし半分はがっかりしてしまう自分がますます恥ずかしくなって、りんごに飴に負けないくらい真っ赤になってしまった。
「いやいや、本心だって。それにほら」
新太郎は、自分のカバンの中から『お徳用ご家庭花火セット』を出してきた。
「せっかく浴衣着てて雰囲気もいいし。お祭りの花火には負けるけど、これはこれで楽しいし、なっ」
最後の「なっ」で、千恵美に同意を求める新太郎に、何度もコクコクとうなづいて答える千恵美は、陽子ちゃんに「今年は好きな人と庭で花火をしたよ」って言ったら、きっとズルイと少し拗ねてみせてそれから、自分のことのように喜んでくれるだろうなと思った。
「あっ、そうだチィ去年俺が取った金魚どうした?」
新太郎の問いに千恵美は得意満面でこう答えた。
「勿論、元気に決まってるじゃない」と。
|
|
|
|